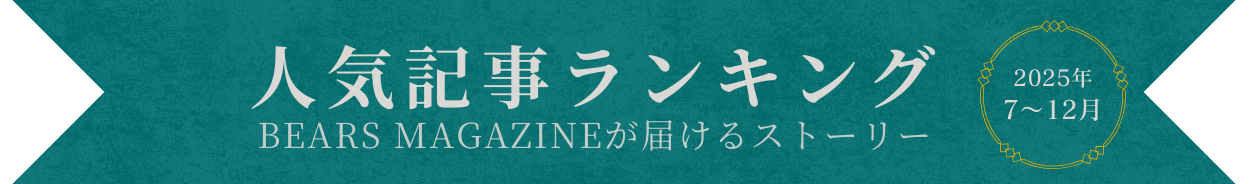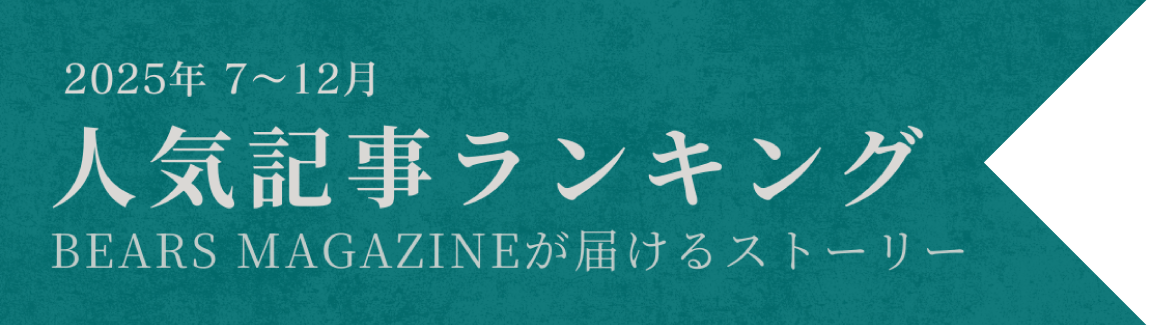現代にも息づく江戸の粋。「神田祭」のこれまでとこれから
千代田区にある神田明神(神田神社)を中心として、2年に一度開催される「神田祭」。例年30万人以上が集結し、街全体が活気に包まれます。今回は、自らも町会の一員として祭りの運営に携わる千代田ゴム株式会社 代表取締役社長 高遠典昭さんに、祭りへの想いや、まちが歩んできた歴史についてお話を伺いました。
江戸の伝統と誇りを受け継ぐ祭り
神田の街が『ワッショイ!』や『ソイヤ!』という掛け声に包まれる中、今年も5月8日の鳳輦神輿遷座祭(ほうれんみこしせんざさい)から5月15日の例大祭まで6日間にわたり「神田祭」が執り行われました。このお祭り一番の見どころは「神輿宮入」。108の町会がそれぞれ持つ大小200を超える神輿が街を練り歩き、神田明神に集まる光景は圧巻の一言です。より一層気合いが入った担ぎ手たちの熱量とその迫力に圧倒されます。

そんな街を挙げて大盛り上がりする神田祭ですが、一説によるとその起源は奈良時代まで遡り、大祭となったのは江戸時代以降といわれています。
幕府が都を江戸に移してから、神田明神は “江戸の総鎮守” として崇敬されており、1600年に徳川家康が関ヶ原の戦いなどで勝つために祈祷を命じ、天下統一を果たした際に盛大な祭礼を行ったといいます。そんな歴史背景から別名 “天下祭” とも呼ばれ、家康が絶やさず執り行うよう命じたことから現代も続いているのです。
活気にあふれる神田の街
江戸時代から変わらず地元住人や祭り好きから愛され続ける「神田祭」。その魅力を深掘りするべく、「神田鍛冶三会町会」の髙遠典昭(たかとお ふみあき)さんにお話を伺いました。昨年5月までお父様が町会長を務め、自身は青年部副部長として活動されています。

――初めて間近で神田祭を見物しましたが、特に宮入の迫力はすごかったです。
髙遠典昭さん(以下、髙遠):明神さんの鳥居の前にまで行くと『さっきまでこんな人いたっけ?』というくらい人が増えて、収拾がつかなくなります(笑)。みんな宮入には並々ならぬ誇りを持っているんですよね。
――髙遠さんの町会は何人くらいが参加していたのですか。
髙遠:まず神田神社の氏子の中に連合、さらに下は町会という構成になります。私たちが所属するのは神田公園周辺にある中神田十三ヶ町連合の「神田鍛冶三会町会」です。今年は800人ほどにご参加いただきました。

髙遠:そのうちほとんどが同好会の方とその関係者だと思います。同好会というのは日本全国のお祭り好きが集まる団体で、地元民と一緒になって祭りを盛り上げてくれています。最近は担ぎ手も減ってきているので、神田祭も同好会なしでは語れなくなっている状況です。
――お神輿を担いでいるのは、てっきり町会に住んでいる方だと思っていました。
髙遠:千代田区という土地柄もありますが、バブル崩壊以降は夜間人口が少ない地域になってしまったんです。それでも以前は法人の会員を巻き込んだりしたこともあったそうですが、最近はコンプライアンスや働き方改革の問題で難しくて。
ちなみに同好会以外で、神田にご縁がある方が参加しているパターンも多いんです。例えば神田で働いている方やお店を出している方、祖父母が昔住んでいたという方もいらっしゃいます。町会の役員は40人ほどいるのですが、千代田区に住民票があるのは多くても10人くらい。いかにお祭りを継続するのが難しいのか考えさせられます。

江戸時代から町人の街として栄えた神田
――現在はオフィス街のイメージが強いですが、以前はどんなエリアだったのでしょうか。
髙遠:千代田区は元々神田区と麹町区にわかれていて、明治時代の初めに合併して今のかたちになりました。佃節[*]で『粋な深川、いなせな神田、人が悪いは麹町』という唄がありますが、麹町は武家屋敷が多くてお偉いさんが多いエリアだったんですよね。一方こっちは町人の街。
神田鍛冶三会町会はいくつかの町が統合しているのですが、鍛冶町は “鍋町” と呼ばれ江戸幕府御用達の鍋や釜をつくる鋳物師が集まっている街でした。さらに日本刀の装飾具などを専門に製作する御腰物金具師(おこしものかなぐし)など、職人が住むエリアだったということが文献で残っています。
*江戸時代、隅田川の船遊びなどで芸者の間に流行した小唄のこと。

――神田には下町のイメージを持っていたので町人の街だったことに納得です。
髙遠:江戸時代は行政区画がしっかりしていて古地図なども残っているので、400年前に誰が住んでいたのかわかるんです。108町会の名前の由来やどう町が変遷したのかを辿ると面白いですよ。
当時、江戸城と街づくりのために職人をかき集めたので、住んでいる人のほとんどが地方からの出稼ぎで、8割が男性。だからこそファーストフードとして寿司文化が根付いたり、元々は “多文化共生” っていう意味合いで懐の広い街だったらしいです。


――すごくお詳しいですね。こういった情報はどこから入手しているのでしょうか。
髙遠:全て歴代の先輩たちからです。飲み会のたびに酔っ払いながら話しているので間違えているところもあるかもしれません(笑)。でも先輩たちとのこういった関係性は神田ならではだと思いますし、隣に住んでいる人の顔も知らない時代にいわゆる “土地の縁” で繋がっているところに魅力を感じます。この辺(神田鍛冶町)を歩いていると、こういう身なりなので結構声をかけてくださるんですよね(笑)。
――世代を超えた繋がりがあるのは素敵なことですね。オフィス街ならではのエピソードは何かありますか?
髙遠:宮入前に休憩していた「ワテラス」は、淡路町二丁目という1つの町会が丸々複合施設になってしまったんです。だからこそ色々と試行錯誤をしていて、10年ほど前から学生が安く住める区画を作りました。その代わりに地域ボランティアとして子供縁日で屋台を出したり、神田祭にも携わってもらっています。就職で神田から離れてしまうので定着率が低いという問題はありますが、体験としてはとても価値ある取り組みだと思っています。
次ページ▶ これからの「神田祭り」とは

髙遠典昭 Fumiaki Takato
生まれも育ちも神田。1946年創業の千代田ゴム株式会社の代表取締役社長を務める傍ら「神田鍛冶三会町会」の青年部副部長として神田祭の運営に携わり、「神田祭」を次世代につなげる活動に取り組んでいる。