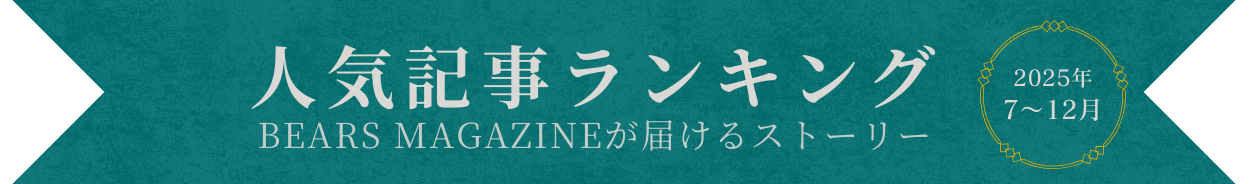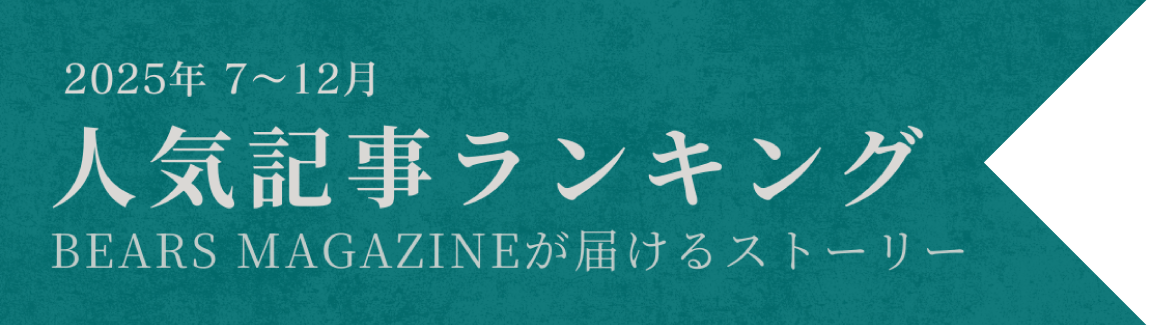市民に愛され、丹下健三の構想を未来へつなぐ
「横浜美術館」
横浜に市民が集い、賑わう場を
かつて横浜の中心部は、関内・伊勢佐木町地区と横浜駅周辺地区に分かれていました。この2地区を一体化するとともに、市民が集い賑わう場の創出と経済基盤の確立を目的に、1983年、広大な造船所跡地の開発事業「みなとみらい21」が始動します。都市機能が整備されたのち、1985年の横浜新都市ビルを皮切りに1991年に国際交流の拠点であるパシフィコ横浜、1993年には横浜ランドマークタワーがオープン。現在開発は最終段階を迎え、オフィス、商業施設、文化施設が集積した、働きやすく住みやすい魅力的なエリアが完成しつつあります。

開発にあたり、都市機能の重要な要素として重視されたのが文化でした。「横浜美術館」は、みなとみらい21地区の文化を担う重要な施設として1981年にいち早く構想が始まり、1989年に開館しました。
“新鮮” だった、美術館運営に関する注文
——開館当時を振り返って、何か印象に残っていることはありますか?
蔵屋:実は悔しいことに、開館記念展には足を運べていないんです。よく通うようになったのは1992年頃からだと思います。当時はまだみなとみらい線が開通しておらず、JR桜木町駅から長い道のりを歩いて行った記憶があります。周囲も開発工事の真っ只中で、何もない中に美術館だけがぽつんと建っている状態でした。その頃はこの美術館が開発計画の中核事業であることも、どのように構想されていったかも全然知らなかったんです。

——前職では「東京国立近代美術館」で企画課長を務めていらしたと伺いました。「横浜美術館」の館長に就任された時のことを教えてください。
蔵屋:まず驚いたのは美術館に対する横浜市の考え方です。着任時に『社会的な存在意義を考えて運営してください』と言われたことがとても新鮮でした。国立近代美術館は、展覧会ごとに様々な方が来るので、どうしても収支に重点が置かれがちです。対してここを運営している横浜市は、『地元の方々にとって有益なこと、そして収支、両方を考えてくださいね』と仰いました。2021年からの工事休館を経て、今年2月にようやく活動を再開したことで、地元の方がどういう人で、どういうことを求めてるのかがいよいよリアルに見えてきました。

リニューアルして見えた、美術館を愛する市民の “顔”
——2025年2月にリニューアルオープン記念展「おかえり、ヨコハマ」を開催されましたね。そこではどんな反応がありましたか?
蔵屋:出品作品の8割が当館のコレクションだったのですが、“横浜の歴史をみんなで考えよう” という新しい視点で再解釈し、企画・展示しました。会場を見ているとお子様が多い印象で、実際に集計してみると約8%が高校生以下だったんです。これは『地元横浜で、いいものを子供に見せたい』と願う保護者の方々の心の現れだと思います。それに「長かったですね」「ようやくできましたね」と声を掛けてくださる方も多く、オープンを心待ちにしていただいていたことを実感しました。
——市民の方々にとって、美術館がどういう存在なのかがよくわかるお話ですね。
蔵屋:そうですね。2021年3月に休館しましたから、当時0歳だったお子さんは4,5歳になっていますよね。美術館がない状態で子育てをなさっていた方々が、待ちかねてどっと来てくださった。そんな印象を受けましたし、それは素晴らしいことだと思います。
ここは市の美術館にもかかわらず、国立規模の大きな施設で、ピカソ、セザンヌ、マグリット、ダリなど錚々たるコレクションを持っている。それでもスタンスはあくまで “市民のための美術館” なんです。これは稀有なことで、市民の方々には『こんなにいい作品を持つ美術館が近所にあるって良いよね』ときっと思っていただけていると信じています。

機能を持たない巨大スペース
——そもそも、なぜ大規模改修を行うことになったのでしょうか?
蔵屋:工事は何年も前から計画されており、空調設備の更新のほか、エレベーターの新設やギャラリーの増設など諸機能のアップデートを行いました。この建物は丹下健三さんによる設計で、丹下さんのご子息である憲孝さんが会長を務めておられるTANGE建築都市設計が施設本体の改修を手がけました。その本体の中に、どんな什器やサイン関係をしつらえて、お客様をお迎えするか考えるために、まず丹下さんがなぜこのような設計をしたのかを勉強することから始めました。調べていくうちに、展示室や収蔵庫といった機能を持つスペース以外がとても大きくとられていることに気付いたんです。

——3階の奥に化粧室がありますが、そのあたりもゆったりとしたスペースに革張りのソファが置かれていますね。ガラス越しにオブジェがゆっくりと動いているところが見え、くつろいだ気持ちになりました。
蔵屋:そちらのスペースを今回 “エスケープゾーン” に定めました。お子様が泣いたときの逃げ場として使っていただけるほか、水を飲んでひと休みしたり、携帯電話での通話もしていただけます。屋外作品を眺めるあの窓も、丹下さんが意図を持って設計されたものなんですよ。


蔵屋:疲れたらすぐ休めるように休憩スペースが多く設られ、また息が詰まらないように外が見える場所も用意したんだと思います。まさに丹下さんの配慮ですね。今回のリニューアルで大きく雰囲気が変わったと言われますが、実はもとの構造にほとんど手を入れていないんです。印象が変わった理由は、丹下さんが設けた “機能を持たない大きなスペース” 。その意図を、30年経って初めて見つめ直したことにあります。
いかがでしたか。
横浜美術館がみなとみらいの街づくりを見守り、市民とともに歩んできた美術館ということがわかりました。後編では、丹下さんの意図を組んだ美術館をどのように表現したのか、具体的にご紹介します。

蔵屋 美香 Mika Kuraya
横浜美術館館長 千葉県生まれ。美術大学で油絵を専攻したのち、大学院で美術史・芸術学を学ぶ。1993年より東京国立近代美術館に勤務し、同館美術課長を経て2016年に同館企画課長就任。 数多くの展覧会を手掛けるとともに、2013年第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展では日本館キュレーターを務めるなど、国内外で活躍。2020年4月、横浜美術館第6代館長に就任。美大進学の理由は漫画家になるためだったとのことで、2021年には「暗☆闇香(くら・やみか)」のペンネームで漫画家デビューを果たしている。