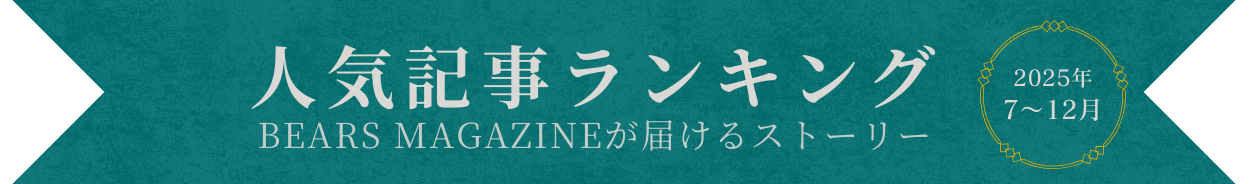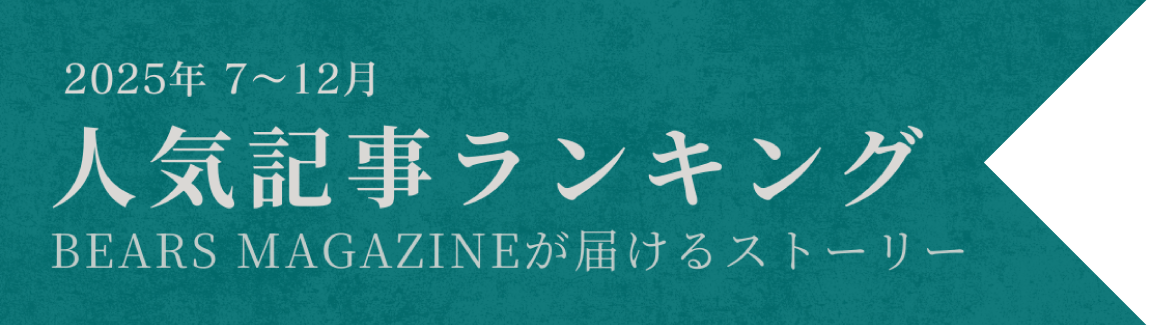日本の伝統技術を現代のデザインと融合し、昇華させる「ubushina」
ubushinaはこうした伝統を取り入れた空間デザインやアートワークを数多く手掛けているブランド。今回は代表を務める立川裕大(ゆうだい)さんに、ブランドの哲学や日本の伝統工芸が秘める可能性についてお話を伺いました。

伝統技術と現代デザインを繋ぐ仲介人
——はじめに、ubushinaについて教えてください。
立川裕大さん(以下、立川):プロジェクト名の「ubushina」は漢字では『産品』と書きます。古語の『うぶすな(産土)』と同義で、 “生まれた場所” “その土地の恩恵” という意味の言葉です。
日本には地域ごとに異なる素材や気候を活かして生まれた多様な伝統技術があります。それらを現代のインテリアや建築に活かすためのプロデュースを行うことを、私たちの使命としています。
——近年、ホテルやレストランなどで伝統技術を活かした素敵なインテリアを目にする機会が増えたように感じます。ubushinaはそういったものをプロデュースされているのですね。
立川:はい、そうです。私たちが担うのは建築家やデザイナーと、職人との間に立ってきっかけづくりから納品までの生産管理をする役割なんです。日本には非常に高い技術を持った職人が多くいます。クリエイターが求めるクオリティやコスト、納期に合わせて数ある職人の技術を組み合わせ、空間やオブジェを設えていくんです。

自国の文化を思い出させた巨匠の言葉
——立川さんはもともと伝統技術の世界にいらしたのでしょうか。
立川:それが、まったく違うんです。私は大学の経済学部出身で、アートやデザインを専攻していたわけではありません。ただ学生時代からデザインに興味を持っていて、特に好きだったのがイタリアの家具でした。まだ『カーサ・ブルータス』も創刊されてなかった時代です。なかでも「カッシーナ」の家具に一目惚れしてしまい『好きなものを仕事にしたい』と、大学卒業後に「カッシーナ」に就職して、イタリアの家具を建築家やインテリアデザイナーに売り込む営業職として働いていました。
——ubushinaはどのようなきっかけでスタートされたのでしょうか。
立川:何度も通ったミラノでイタリアデザインの巨匠、エンツォ・マーリさんと出会ったのが大きなきっかけでした。ある時私はマーリさんに『イタリアのデザインも良いけれど、君の足元にもすごいものがあるじゃないか』と指摘されたんです。そこで改めて日本に目を向けると、本当に “すごいもの” ばかりで。日本の伝統技術と向き合う仕事を始めたいと思いました。
頃合いを同じくして富山県高岡市でデザインについての講演をする機会があったのですが、滞在中に訪れた工房で職人の技術の高さを目の当たりにし、とても衝撃を受けたんです。そこから紹介で繋がっていき、ともに仕事をする職人の輪が全国に広がっていきました。

想いを初めて具現化した「Hotel CLASKA」
——イタリアのデザイン界に影響を受けて、日本の伝統へと回帰されたのですね。ubushinaは2003年に立ち上げたと伺っていますが、そこからどのようにしてブランドを作り上げていったのでしょうか。
立川:「Hotel CLASKA」の内装材や家具・照明などを伝統技術を用いて製作したことが大きな転機になりました。当時エッジの効いたデザインのホテルはまだ珍しかったので、とても注目されましたね。建物の中にオフィスを構えていたので、ショールーム代わりにお見せしていました。

——「Hotel CLASKA」は2020年に閉館してしまいましたが、今もデザインホテルの先駆けと言われていますね。
立川:海外の方にも高く評価され「世界のクリエイターの溜まり場」と言われていたこともあります。「Hotel CLASKA」の内装は高岡をはじめ、全国各地の職人の力を借りてつくりあげました。日本古来の技と素材を現代のデザインに再編集して融合させる実験的な試みでしたね。「Hotel CLASKA」の成功は、日本の職人技が世界に通用することの証明となりました。


(下)同ホテルのロビー。真鍮鋳物のライトがやわらかな光を放っている。
(デザイン:Intentionallies 写真:Nacasa&Partners)
現代デザインに溶け込む伝統技術の数々
——ubushinaではこれまでどのようなものを手掛けてこられたのでしょうか。
立川:レストランや商業施設、ホテルから個人邸まで幅広くお仕事をさせていただきました。ラグジュアリーブランドの店舗内装を手掛けることも多いですね。このショールームにも皆さんが良く知っているヨーロッパのブランドの方が頻繁にいらっしゃいますよ。

立川:ラグジュアリー系ホテルの仕事も多く、例えば沖縄にあるホテルでは、さとうきびを使った沖縄伝統の「ウージー染」という染物を使用したアートワークを手掛けました。草木染は素材によって仕上がりが大きく左右されるので、さとうきびの収穫エリアまで配慮しながら製作しました。

立川:使用する素材も和紙や鋳物、竹細工、組み紐、ガラス工芸などさまざまです。ロンドンの設計事務所とともにデザインした邸宅では、ソファの貼り地に民芸品の「刺子織」を使用したり、テーブルも銅板に漆を塗って仕上げたりと、昔からある技術をたくさん採用していただけました。一見するとコンテンポラリーな空間でありながら、一つひとつを紐解いていくと伝統工芸が上手く活用されています。

“守破離” の精神でつなぐ伝統工芸の未来
——今までにないような取り組みばかりですが、職人から難色を示されることはないのでしょうか。
立川:それはあまりありません。たしかに職人の事情も踏まえないでただ一方的に『納期に間に合わせてくれ』『予算に収めてくれ』と言うと反発を受けてしまうでしょう。しかし私たちは職人それぞれの持ち味や性格に精通していて、与えられた条件の中で最高の作品を作り上げるためにどうすれば良いかを共に考えるようにしています。だからこそ強い信頼関係で結ばれているのです。
——職人の皆さんも納得感を持って仕事ができているのですね。
立川:私の座右の銘に “守破離” という言葉があります。『先人が築いた型を “守” り、後にそれを “破” り、いずれそこから “離” れて新しい型へと至る』という意味です。型がある芸能や工芸には必ずある概念ですが、これを続けていかなくては伝統を守っていけません。この “守破離” を促していって、伝統工芸の未来をつくっていくことも私たちの使命だと思っています。

*NCルーター:数値情報を入力することで、繰り返し同じ精度でくり抜き加工ができる装置
立川:そんな私たちがお願いする仕事は従来の型にはまらないものばかりです。それに応える職人側からするとこうした外的な刺激を受けることで新たな気づきを得て、さらに活躍の場を広げられるかもしれない。そういった可能性に気づいているからこそ、私たちとともに仕事をしてくれているのだと思います。
海外に見る日本の伝統工芸との “差”
——立川さんから見て日本の伝統工芸はどのような状況なのでしょうか。
立川: “危機的状況” と言えると思います。職人たちは素晴らしい技術を持っているにもかかわらず、売り上げにつながらないことで廃業していく工房も少なくありません。せっかく修行をして職人になっても『生活が不安定だから』と諦めてしまう若者さえいて、後継者の数も急激に減少しています。
一方で、ヨーロッパの伝統工芸を起点としたラグジュアリーブランドに目をやると、職人たちは安定した立場で高度な技術を磨いています。この違いは何なのだろうかと考えると、彼らはブランド力やマネタイズする力が圧倒的に強いんです。

立川:日本の伝統工芸も技術では全く負けていないどころか、他のどの国にも真似できないような素晴らしいものを持ってます。 しかしそれをビジネスとして展開することに弱いがゆえに、職人の足場がおぼつかない。日本の伝統技術を発展させていくためには、誰かが間に入ってより職人が活躍できる場をプロデュースしなければならないと思っています。
——ubushinaがこれから力を入れていきたいことはありますか?
立川:私はよく自分たちのことをIT用語になぞらえて “ミドルウェア” と呼んでいます。私たちは職人でもデザイナーでもありませんが “ハードウェア” をつくりだす職人と “ソフトウェア” を提供するデザイナーをつなぐ存在、つまり “ミドルウェア” として欠かすことができません。そこが弱いと、職人の活躍の場は狭まっていってしまうんです。だからこそそんな仕事の大切さをもっと伝えていき、そこにやりがいを感じてくれる若者が増えてくれることを願っています。

さまざまな空間やアートワークに日本の伝統技術を採り入れ、唯一無二の作品をつくり出しているubushina。その想いは『伝統の行方を創造する』という使命感から生まれています。ubushinaではオーダーメイドを基本としていますが、2023年にはプロダクトを製作し世界に発信する「AMUAMI」というブランドをスタートさせました。後編ではギャラリーである「編阿弥庵(あむあみあん)」を訪ね、その世界観をご紹介します。

立川 裕大 Yudai Tachikawa
1965年、長崎県生まれ。「ubushina」を立ち上げ、オーダーメイドで日本の伝統技術を先鋭的なインテリアに仕立てるスタイルを確立する。2016年には伝統工芸の世界で革新的な試みをする個人団体に贈られる「三井ゴールデン匠賞」を受賞。2023年には日本の技の粋を集めたプロダクトブランド「AMUAMI」をスタートさせ、職人の仕事を世界に届ける活動を加速させている。